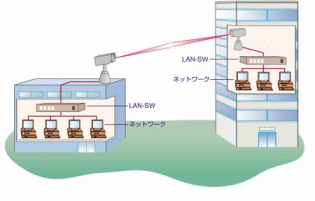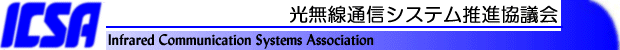
10/08/2003 TOPICS-03020-(1)
光ワイヤレス通信技術の新展開
─光ワイヤレス通信技術調査委員会の活動から─
当記事は、財団法人光産業技術振興協会(OITDA)のご好意によって掲載の許可をいただいたものであり、同協会のホームページならびに機関誌「オプトニューズ」に掲載されています。■屋外光無線通信と衛星間光通信の動向
通信総合研究所: 有本 好徳 氏
1. はじめに
本稿では、レーザ光をレンズや望遠鏡で指向性の鋭いビーム(コリメート光)に整形して伝送する空間光通信システムの開発動向について紹介する。この代表例は、ビル間等の近距離の大気中における空間光通信(ここでは屋外光無線通信と呼ぶ)と、人工衛星や宇宙ステーション、地上を結ぶ衛星間光通信である。
このうち、波長が800 nm近辺の近赤外レーザを用いる屋外光無線通信システムは、画像伝送、LAN間接続やブロードバンドインターネット時代のアクセス系として有効であるばかりでなく、光ファイバ網や無線通信事業者のバックアップとしてもその有効性が見直されてきている。
一方、衛星間光通信は1980年代にNASAやヨーロッパ宇宙機関(ESA)で研究開発が開始された後、1990年代半ばに最初の地上局と衛星との通信実験が日本で行われ、これに続いて多くの実用化計画が発表されたものの、未だに実用化には至っていない。しかしながら、この間の研究開発の成果が最近の屋外光無線通信の分野に応用されようとしている。
2. 屋外光無線通信システム
2.1 開発の経緯
屋外光無線通信は、1960年代初めのレーザの発明と同時に通信への応用が検討され、NTT(当時の電電公社)が中心となり様々な実験が行われた1)。しかし、波長の短い光は大気中の霧、雨の水滴や煙霧、スモッグなどにより著しく減衰する2)ため通信回線として十分な安定性を得ることが不可能であるとの結論に到った。その後、光空間通信はTVのリモコン等非常に数多く使われては来たが、通信システムとしてはファイバ通信の陰に忘れられた存在となっていた。
しかし、1990年代になると電波資源の逼迫と映像伝送など通信量の大きな需要とデジタル化が顕著となってきた。そして、インターネットの爆発的普及と共にネットワークのIP化という構造的変化が生じてきた。こうした流れの中、屋外光空間通信は、まず映像伝送など大きな伝送容量を必要とする分野で利用され始め、やがてコンピュータネットワークの中でTCP/IPプロトコルが主流になるに従い、散発的な誤り発生など回線品質の劣化があっても大容量通信のメリットの方が大きいとの認識が高まり、図1に示すビル間などの近距離のネットワーク接続に利用されるようになってきた。
利用の拡大と共に装置性能も向上してきており、当初10 Mb/s程度の通信速度が主流であったものが、現在では1 Gb/sを超える速度の装置も実用化されている。また、利用分野も拡大し、最近では私的ネットワークでの利用以外にも自治体等の自前回線の一部など地域的イントラネット網へも適用されている。また、交通管制システムなどの社会インフラへも適用されてきている。北米では、屋外光無線通信による地域通信事業を行う事業者も現れてきており、今後は近距離アクセス回線への適用が期待されるところである。実際に、米国では9.11同時多発テロで壊滅的打撃を受けた通信網の復興に威力を発揮し、その有効性が実証された。
図1 屋外光無線通信によるビル間ネットワーク接続2.2 システムの特徴
光無線通信システムは、離れた二地点間の自由空間を伝搬路として利用する無線通信の一種であり、マイクロ波を用いた無線通信システムと比較すると、波長が極端に短いことを除けばその回線の特徴や設計思想は多くの点で共通している。無線通信では、公道や河川越えもしくは地中埋設といったケーブルの敷設コストが不要で、その許認可や工事期間もなくなるため迅速な導入が可能となる。また、私的にケーブル敷設が困難であった場所でも回線構築が可能であり、一旦構築すれば公衆回線に接続するために必要だった回線使用料は不要となる。しかしながら、マイクロ波では周波数資源が逼迫しており、周波数割り当てや免許の問題、同一あるいは隣接する周波数を用いるシステムからの干渉の問題があり、高速大容量の通信を実現することは困難である。
これに対して屋外光無線通信システムは、鋭い指向性を持ったレーザビームを用いることにより他の通信システムや他の電子機器との干渉問題が無くなるので、太陽光や強い反射光が直接装置に入射しないように配慮するだけで、比較的自由に通信リンクを設定することができる。干渉が少ないということは、通信を第三者に傍受されにくいことを意味し、セキュリティに優れた通信システムを提供することができる。しかしながら、地上で光を伝送する場合、伝搬特性が気象条件の影響を受けやすく、特に霧や煙霧等により大きな減衰を生じるため、回線稼働率を確保すると運用距離が短くなる。また、指向性が鋭いレーザ光を用いているため、装置の設置調整が電波に比べると若干難しい。
2.3 利用分野
光無線通信の利用形態としては、ビル間を接続する私設回線が主流であるが、近年、地方自治体による市域やその周辺地域をも含む地域ネットワーク網へも適用されている。また、「学校インターネット」プロジェクトなど大規模なイントラネットの一部として利用されている事例もある。さらに、インターネット需要の拡大に伴い、無線によるアクセス回線(FWA)の提供を行う事業者が多くなってきたが、この中に屋外光無線通信システムを使った地域通信事業やISP事業を提供しようとする動きがあり、北米ではサービスを開始した事業者が現れ始めた。これは、都市部においてビジネス用の大容量の回線を短期間にかつ安価に提供するために、光ファイバが引き込まれているビルからファイバ未整備のビルに対して、光ファイバの支線として光無線通信システムを用いるというものである。一方、移動体通信の拡大に伴い基地局整備の迅速化やスポット需要及び電波不感地帯解消、需要過剰地帯対策のため、極小セル局設置の需要が大きくなってきており、基地局間通信用に光無線通信システムの利用が始まっている。
しかしながら、日本ではファイバが加入者の近くまで既に来ており、比較的容易にファイバが引き込める環境にあり、北米のような積極的な動きはまだ見られない。現在、ベンダ各社やシステムインテグレータ、通信事業者等が参加するビル間高速光空間通信網推進協議会3)や光無線通信システム推進協議会といった団体が、屋外光無線の啓蒙、利用促進、標準化等の活動を行っている。
2.4 要素技術
指向性を持った光を送信、あるいは受信するための光アンテナ(望遠鏡)、変復調部を含む送受信機が光無線通信装置の基本的な構成要素である。送信機の光源には、300 m程度以下の短距離伝送には発光ダイオード(LED)が、長距離の大容量通信には半導体レーザ(LD)が用いられる。また、受光用のデバイスには、シリコンフォトダイオード(Si-PD)あるいは高速・高感度が必要な場合にはアバランシェフォトダイオード(Si-APD)が用いられている。これらの半導体デバイスの量子効率と大気の吸収損失特性から、レーザの波長には800 nm帯(760〜860 nm)が用いられる場合が多い。ただし、この波長帯域でも800 nm以上にはいくつかの大気ガスの吸収線があり、安定な伝送には大気ガスの吸収線の少ない785 nm付近が比較的多く用いられている。デジタル伝送の場合、光の強度に信号をのせる強度変調・直接検波方式が用いられるが、携帯電話の基地局間伝送やCATVのようなアナログ伝送の場合には一定の周波数帯域内で複数のキャリア周波数に変調信号を乗せる副搬送波多重通信を用いる。この場合、性能を維持するための所要信号雑音比が大きくなり、伝送距離も短くなる。
2.5 技術開発動向
(1) 高速大容量化
ギガビットイーサネットの普及と共に、バックボーンのLAN間接続に要求される屋外光空間通信システムの能力も1 Gb/sを求められつつあり、これに対応した製品が発売されている。また、WAN回線での利用を考えた場合、2.5 Gb/sは近い将来必要な帯域となると予想され、実際に製品も発表され始めているし、波長多重(WDM)技術を応用した2.5G×4波長=10 Gb/sの発表も行われている。1 Gb/sを超える容量を実現するために、VCSEL(Vertical Cavity Surface Emitting Laser: 面発光レーザ)の使用や波長1550 nm帯の光ファイバ通信技術の応用が検討されている。
(2) アイセーフ波長への移行
光通信回線を高速化する最も簡単な方法は光出力を増加して変調速度を上げることであるが、光無線通信システムの利用が広がってくると安全性の問題、アイセーフティの確保が装置の設置・運用時に必須の課題となってくる。このため、新しくリリースされる製品の中に、目に安全な1550 nm帯の波長域を使った装置が北米のベンダを中心に現れてきた。現状では、デバイスのコストが高いこと、シングルモードファイバを対象に開発された光デバイスに、空間光をいかに効率的に結合させるかが課題である。
(3) 信頼性の向上
屋外光無線通信システムが通信事業者の回線として認識されていない理由の一つに、稼働率、特に気象に対する影響が十分に評価されていないことが挙げられる。これに対しては、実際の伝送路における大気伝搬特性の測定し、その結果を評価した上で、回線の設計手法を確立することが求められる。このため、2001年10月から1年間にわたる伝搬実験が光無線通信システム推進協議会「光伝搬特性調査WG」により実施され、都心の1.2 kmの伝搬路で99.9 %以上の稼働率が得られるとの報告がまとめられている。
また、システム全体のコストと稼働率の最適化を図るために、光通信回線とマイクロ波やミリ波の無線をハイブリッド化して霧による回線断を回避する方式や、1対多(Point to Multipoint)接続、メッシュやリング状の網構成の工夫により稼働率を確保しようとする考えもある。他にも設置調整や設置点の不安定さを除去し、ビームサイズを小さくすることで回線マージンを増すための自動捕捉・追尾機能や、瞬断を回避し、回線マージンを確保するためのマルチビームダイバーシティ受信等の各種技術の開発が行われつつある。こうしたハードウェア技術のみならず、誤り訂正符号など様々な技術を駆使することも技術的には可能となりつつある。
参考文献: 1) Takeshi Ito, et al.:"Optical PCM Transmission Experiment Through the Atmosphere" The Trans. of the IECE of Japan, Vol. E60, No. 11(1977) 2) 森田, 吉田:"大気中伝搬における光波の減衰特性" 通研実報, 18, 5 (1969), pp. 1165 3) ビル間高速光空間通信網推進協議会(OBN): http://www.obn.ne.jp/
| TOPICS-03020 | 次のページへ |
出典: OITDA 「オプトニューズ」 No.5 2003 通巻137号
このホームページの著作権は、光無線通信システム推進協議会に属します。無断転用・転載を禁止します。
光無線通信システム推進協議会
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1−4−1 日土地ビル 14F
TEL:03-5510-8596 FAX:03-3592-1103